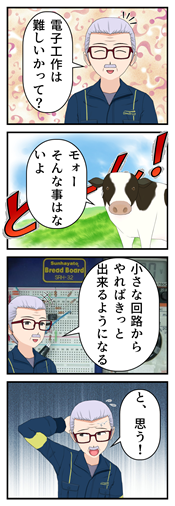[中級の電子工作テスト]
CANONデジ一で遊ぶ
PIC24F RTCCでカレンダー
PICで赤外線通信
PICでシリアル通信
FT232RL変換モジュール
K型熱電対 AD595CQ
K型熱電対のテスト MAX6675
連枝でラダープログラム
連枝でステッピングモータ
各種デバイスのテスト
[シーケンス回路テスト]
リレーシーケンス
[車載用電子工作テスト]
電源の取り方
[PCBCAD]
EAGLE CAD
[掲示板]
電子工作のテスト工場BBS
[リンク]
工作お役立ちリンク集
[電子工作のテスト工場]
表紙[TOP]へ戻る
[電子工作系]
Sivanyan_Radioのブログ
(↑↑管理人のブログです)
GAMEってたのすぃー
電子回路実験教材の部屋 RLC
電子マスカット 必見[MP3]!
kunioのホームページ AVR+MP3
なひたふ電子
ワタヤンの日記
BLUE's electronics room
isi's 趣味の電子工作
獣医さんの電子工作とパソコン研究室
電子用語集Web
YS電子工作ラボ
(↑↑管理人のブログです)
[プログラム系]
信彦の家
[SNS]
電子工作の広場SNS
[写真]
シャッターを押した瞬間
|
事故が起きないように設置したまま走行するのはやめましょう 車載用には車載用の試験をクリアした半導体が必要です。 また、自分で制作したものが原因で生じた事故には保険が適用されない可能性があります。 車に載せる電子工作をする場合、マイコンを使用しようとすると電圧の違いで使えません。 そこで電圧を変換するわけですが、その方法を簡単に説明します。 まず通常の国産車はDC12V電源である事を想定しています。とりあえず車の電圧を確認して下さい。 トラックや外車は特に要注意です。DC12VからDC5V(マイコン用電源)を作るのに手っ取り早いのが三端子レギュレータを使うことです。 秋月電子通商で小さな5V用三端子が売っているのでそれを利用すると便利です。 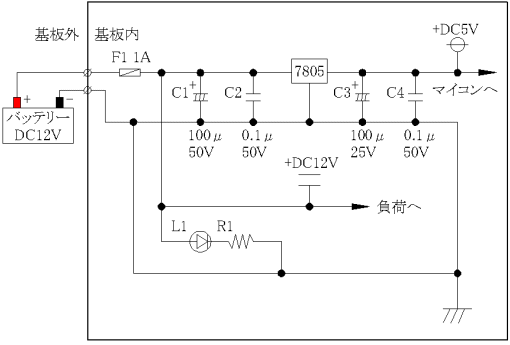 回路は上図のようになります。基板外はバッテリーしか書いていませんが、キーと連動しないと乗っていない時にバッテリーが減ってしまいます。 こんなページを作っておきながら車の事をよく知らないのでどうすればいいのかはわかりません。 キー連動する場合はシガーから電源をとるという間抜けな事をやっています。分からない人は同じようにシガーから電源をとりましょう。 シガーもキーと連動してない車種があるのも事実なのでその点も注意が必要です。 バッテリーから直に回路へ電気を供給するのは危険です。必ずヒューズを通しましょう。 ヒューズボックスの空きが分かる人はヒューズボックスから取ってもいいですが、わからないので基板上に載せています。 容量はその時々の負荷によりますのでご注意下さい。 7805(三端子レギュレータ)への電源回路と負荷への回路(DC12V)を分けて書いています。 これは7805の発熱を抑えるためです。落とす電圧分(DC12V−DC5V)と流れる電流で三端子は発熱します。 その発熱量が大きくなると放熱の為の工夫が必要になります。そこで電流を少ししか流さずに使用する事により発熱を抑えようと考えます。 電流を少ししか流さないとなると、DC5V回路が必ず必要なのがマイコンだけであるという事に気付きます。 よって、DC5Vはマイコンのみの電源として使用します。また、マイコンを高速動作させるとその分電流を消費するのでなるべく低速で動作させます。 内部発振回路を利用して4MHzで動作させられれば数mAですみます。その他の負荷はDC12Vで動作させます。 この方法は後記します。今回の回路ではパイロットランプ(電源ランプ)L1をDC5Vから取らずにDC12Vから取っているのも発熱を考慮した回路だからです。 |
|
マイコンから直接12Vの負荷を操作する事は出来ません。
そこでトランジスタを用いて12Vの負荷を制御します。
例としてDC12VでLEDを点灯させる回路を描いてみました。 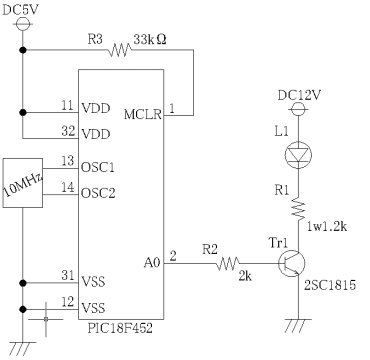 マイコンから出力された信号はTr1のベースからエミッタに流れます。 その信号がスイッチとなり、Tr1のコレクタからエミッタに電流が流れます。 そしてLEDが点灯します。回路的には簡単ですが、5V時と違って計算しないといけないのが発熱量。 この回路では流している電流が少ないのであまり関係ありませんが、次の場合を考えてみましょう。 電源電圧5VでLEDに30mAを流した場合、「W=V×I」で計算すると0.15Wであるとわかります。 よって、1/4W抵抗(0.25W)の抵抗を使用すれば大丈夫だとわかります。 しかし電源電圧12VでLEDに30mAを流した場合0.36Wになります。 この場合は1/4W抵抗では許容範囲外である事が理解できると思います。ここでは1/2Wか1W程度の抵抗器が必要になります。 発熱量を抑えるために抵抗値を上げて電流値を下げ、目的の輝度が保てるのであれば消費電力は少なくするように設計する事をオススメします。 |
Copyright (c) 2007-2022 amahime All Rights Reserved.